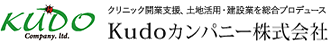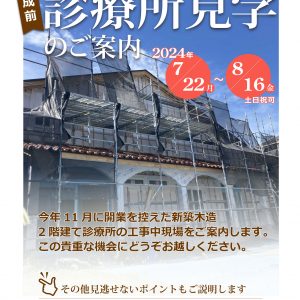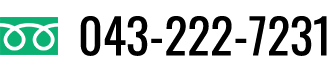開業する先生に捧ぐ No7.資金調達方法
医療経営建替え・開業
クリニックを開業する先生に捧ぐ No7.【資金調達方法について】
クリニック開業では、テナント契約や内装工事、医療機器等の初期投資に相当のお金がかかってしまいます。
事業収支計画では、必要となる資金をどのように調達できるかの点も非常に重要な要素となります。
クリニック開業のための資金調達方法を8つに分け、その特徴と注意点等をお話しします。

- 自己資金
勤務時代の預金や退職金等の自己資金は、基本的な財源です。
多ければ多いほど良いのは言うまでもありません。
自己資金は、平均して開業資金全体の10%~20%といわれますが、個人の事情も様々で、「自己資金はほとんど出さずに開業した」というケースも少なくありません。
ただし金融機関の融資審査においては、拠出する、しないにかかわらず預貯金残高が
多いほど事業に計画性があり、無理のない開業であると評価されるようです。
また一方で「無借金」であることにこだわるケースもありますが、無理に自己資金で
収めようとするより、ほかの調達方法と併用し、必要十分な投資をすることが肝心です。
- 親族からの資金提供
ご両親や親族から贈与や借入で資金提供を受ける方も多いでしょう。
親族による借入の場合、金融機関の融資評価は実質的に自己資金と見なされることもあり、できれば有り難く遣わせて頂きたいところですが、以下注意すべき点があります。
・返済を考えない場合、当然贈与税がかかる可能性があり、特例を活用する場合などは税理士に相談して有利な方法を選択してください。
・借入の場合でも実質的に贈与とみなされることが あり得るので、契約書をしっかり作成し、適正な利息を乗せ、銀行振り込みなど記録が残る形で返済を行ってください。
- 助成金
助成金とは、公的機関が政策的目的で事業者に支給するお金です。
返済が必要ないのが大きなメリットで、中小企業庁が行う創業補助金や、厚生労働省が行う労働系助成金、自治体によるスタートアップ助成金など様々なものがあります。
創業時には、使える助成金がないか、確実にチェックしたいところです。
助成金は情報収集がものをいいます。
業種により受けられる助成金が異なることも多いため、先輩開業医や周囲の専門家から情報を集め、検討することが重要です。
- 融資
自己資金や助成金を検討した後、不足資金が生ずる場合は金融機関等からの借入を考慮します。
クリニック開業に対する融資は、民間銀行の多くが専門部署を立ち上げるなどして比較的積極的に取り組んでいますが、それ以外には以下のようなところが考えられます。
- 独立行政法人福祉医療機構(WAM)
社会福祉法人や医療機関への融資を行う厚労省所管の独立行政法人。
固定・低利で、長期資金を調達できる。クリニックは、主にへき地での開業が対象となります。
- 日本政策金融公庫
中小企業向けの融資を行う、クリニック開業では最もオーソドックスな機関。
固定・低利で、比較的定型的な審査が行われます。
無担保・無保証融資枠もあるようです。
- 地方自治体による制度融資
開業予定地の自治体により、創業時に融資や金利補てんを行っていることがあります。
基本的に信用保証料がかかります。
- 医師信用組合
医師会員の相互扶助の活動を行う金融機関。低利で担保評価も高い傾向があります。
東京など、都道府県によって組合が存在しないこともありますので、医師会に入会する場合はチェックしてください。
開業資金融資は、ドクターの経歴や専門性、また事業の特徴を総合評価して審査されますが、いずれにしても実績のないところへの融資であることから、いかに将来性のある事業かをしっかりアピールすることが大切だと思います。
先生方が開院なされるクリニックの相対的な優位点などをうまく盛り込んだ事業計画を作り、少しでも良い条件で資金調達できるようにしたいものです。
Kudoカンパニー株式会社
医療福祉施設開発グループ
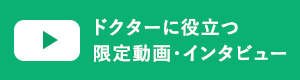
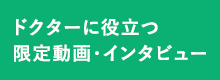
まずはご相談ください
Kudoカンパニーは、お客様の置かれた状況に合わせた柔軟な対応を得意としています。
まずはあなたのお悩みについてお聞かせください!
- 電話でのお問い合わせ 043-222-7231